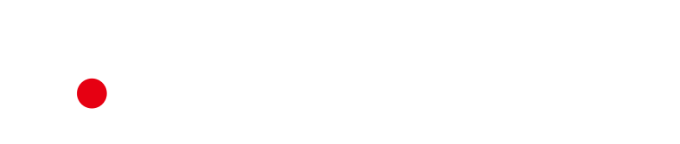「想い、伝える。触れる感動。」-印刷にかける想い-
大阪・天王寺区を拠点に、名刺やパンフレットといった軽印刷から、化粧箱・紙製什器の製造、その他にもSMATRAY、アクリルキーホルダーや折り畳みが出来るPATAXという斬新なアイデアで快進撃を続ける株式会社サキカワ。近年では企業コラボのガチャガチャなどで全国へと市場を広げているのも同社の強みだ。そんな株式会社サキカワの歩みは1950年、靴箱の製造からスタートした。創業の背景には、神戸で靴づくりを営んでいた一族の存在だ。靴の運搬や保管に欠かせない箱を内製化するために立ち上げたのが株式会社サキカワのルーツである。やがてパッケージ事業の拠点を大阪・天王寺へ移し、創業から75周年を迎える企業に成長を遂げた。
その株式会社サキカワを引っ張る四代目社長が久保貴啓氏である。久保社長は、自身が思い描く経営の理想像と現実のギャップに悩みながらも、従業員の幸福を願う経営を突き進んでいる。そんな久保社長の経営に対する胸中に迫ってみた。

俳優を夢見た青年が、挫折を味わい覚悟を決める
大阪府南部、和泉市や堺市を含む泉北地域。その地で生まれ育った久保社長は、高校卒業後、俳優を志して上京した。
しかし、待っていたのは華やかな世界ではなく、現実との厳しいギャップだった。所属した劇団での活動は、地域の学校を巡回し、子どもや学生たちに向けて舞台を届ける日々。演劇だけでは生活が成り立たず、複数のアルバイトを掛け持ちしながら、稽古に励む苦しい二重生活が続いた。
それでも10年間、夢を信じて挑み続けた。
ただ、久しぶりに会う友人たちの安定した社会人生活の話を聞くたびに、自分だけが取り残されているような焦りや虚しさが胸に残ったという。
「“社会人”という言葉の響きに惹かれたんです」と久保社長は当時を振り返る。
そして28歳のとき、俳優の道に終止符を打ち、就職を決意した。
入社したのは、親戚である叔父が経営する株式会社サキカワ。
とはいえ、当初の目的は“安定した収入”であり、仕事に対する意識もアルバイト感覚のままだったと率直に語る。
恩義ある叔父に頭を下げて入社したにもかかわらず、これまでに3度も辞表を提出したことがあるという。
「そんな自分を引き留めてくれたのは、一緒に働く仲間たちでした。彼らの支えがなければ、今の自分はありません。」
迷いと葛藤の中で、久保社長は“人とのつながり”の大切さを痛感する。
仲間との絆が、仕事への覚悟を育て、経営者としての礎を築く第一歩となった。
劇団の団長気分で引き受けた“社長業”─
待っていたのは理想と現実の深い溝
ある日、叔父であり当時の社長から、突然こう告げられた。
「久保、お前、社長にならないか?」
思いもよらない申し出だった。
その頃、株式会社サキカワは年々売上が減少し、後継者も見つからないという厳しい状況にあった。親族という縁もあり、白羽の矢が立ったのが久保社長だった。
しかし、過去に何度も辞表を提出してきた自分を思い返し、すぐに口をついて出た言葉はこうだった。
「私には社長の器はありません。他にふさわしい方がいるはずです。」
それでも先代は、静かに、そして重い言葉を残した。
「お前がやらないなら、この会社を畳もうと思う。」
その一言が胸の奥に突き刺さった。
「それなら、私がやります。」
逃げることをやめ、腹を括った瞬間だった。
「正直、最初は“劇団の団長を務めたときと同じような感覚でできるだろう”と思っていました」と笑う久保社長。
しかし、その考えがいかに浅はかだったかを、就任直後に思い知ることになる。
社長に就任して間もなく、彼を待っていたのは、理想と現実のあまりに大きなギャップだった。
「社長が右と言えば左も右になる」──そんな古いリーダー像を信じ、厳しさこそ正義だと信じていた。
だが、その姿勢こそが、次第に現場との距離を広げていたのだ。
経営者としての船出は、まさに孤独と混乱の中で始まった。
信頼が崩れた日──
社長としての最初の試練
かつては同じ目線で汗を流した仲間たち。
しかし、久保社長が“社長”という立場になった瞬間から、その関係は一変した。
「従業員としての振る舞い」ではなく、「経営者としての姿勢」を求められる。
挨拶の仕方ひとつにも妥協を許さず、礼儀や基準を厳しく求めた。
それは本人にとって、会社を背負う者として当然の責任感からの行動だった。
だが、現場から見れば、それは“押し付け”に映ったという。
さらに追い打ちをかけたのは、現場に根強く残る「先代のやり方」だった。
新しい方針をどう受け入れてもらうか──久保社長にとって、最初の大きな壁だった。
そして、就任から1年目の夏。
長期休暇に入った直後、彼の自宅の郵便受けに、手書きでびっしりと綴られた十枚近い手紙が届いた。
封を開けると、そこには信じがたい言葉が並んでいた。
「私たちは先代の社長に雇われたのであって、あなたに雇われたわけではない」
「社長になったからといって、すべてあなたの言う通りにしなければならないのか」
それは、まるで心の距離を突きつけられるような内容だった。
「自分が築いてきたものが一瞬で崩れ落ちるような感覚でした」と当時を振り返る。
眠れぬ夜が続いた。
「自分は社長の器ではないのではないか。このままでは会社を潰してしまうかもしれない。皆を不幸にするのではないか。」
そんな思いが頭を離れなかった。
失望と不安の中で、久保社長にとって初めての“本当の試練”が始まったのだった。
失望と不安の中で、久保社長にとって初めての“本当の試練”が始まったのだった。
経営とは、己を映す鏡──
フィロソフィが教えてくれた経営者が生きる道
が折れかけていた久保社長は、旧・大和盛和塾(※京セラ創業者・稲盛和夫氏の経営哲学を学ぶ経営者の勉強会)の代表であった脇本氏に一本の電話をかけた。
「もう盛和塾をやめます」――絞り出すような声だった。
当時、二人の関係は挨拶を交わす程度。それでも脇本氏はすぐに駆けつけ、3時間にわたって黙って久保社長の話を聞き続けた。
「色々と大変だったね。今抱えている悩みは、すべてフィロソフィが解決してくれる。会社のフィロソフィを一緒に作ろう。僕の会社のフィロソフィブックをあげるよ。」
そう言って差し出された一冊の本。
それが、久保社長の人生を大きく変えるきっかけとなった。
「人としてどう生き、どう働くか」――その原点を見つめ直し、自社にその哲学を根付かせる決意を固めたのだ。
しかし、現実は甘くなかった。
これまでの強圧的な経営への反発から、「私たちは作らない」「完成しても参加しない」と公然と反発する社員もいた。
やがて多くの社員が去り、最後に残ったのは、昔からの従業員わずか5人だけ。
「でも、この5人がいたからこそ、自分は救われた」と久保社長は静かに語る。
フィロソフィを学ぶほど、それは“社長自身を映す鏡”になっていった。
「社長だから弱さを見せてはいけない」――そう信じていた過去の自分。
しかし、真の強さとは“弱さを隠すこと”ではなく、“弱さを受け入れること”なのだと気づいた。
迷いや葛藤を隠さず、正直に社員と共有し、全員で向き合う。
その姿勢が次第に信頼へと変わり、職場に“心でつながる関係”が生まれていった。
「ありのままの自分をさらけ出してこそ、本当の仲間になれる」
久保社長はそう語る。
この気づきこそが、現在の経営スタイルの原点となった。
愛を忘れた経営は、続かない──
家族の言葉が教えてくれた経営の原点
久保社長は、経営の話だけでなく、自らの人生経験についても率直に語る。
「当時の自分は、本当に傲慢だったと思います」――そう静かに振り返る。
会社を軌道に乗せようと必死だったあの頃。
寝る間も惜しんで仕事に打ち込み、家庭を顧みる余裕はほとんどなかった。
その結果、妻とは別々に暮らすことになってしまったという。
そんなある日、たまに会える幼い息子との何気ない会話が、久保社長の人生を大きく変える出来事となった。
息子と出かけた帰り道、車の中で「疲れてるだろう?寝ないのか」と声をかけると、満面の笑みでこう返ってきた。
「父ちゃんと会えるのはたまにしかないから、寝たらもったいない。」
その一言に胸が熱くなり、思わず涙がこぼれた。
息子を妻のもとに送り届けた後、その話をすると、妻は冷静に、しかし厳しく現実を突きつけた。
「みんなの幸せとか言ってるけど、自分の息子ひとりも幸せにできてないじゃない。そんな人が、どうして他の人を幸せにできるの?」
その言葉に、深く打たれた。
“家族の幸せ”を置き去りにして、会社のために走り続けてきた自分。
誰よりも近くにいるはずの家族の想いを、何ひとつ理解できていなかった――。
久保社長は、そのとき初めて気づいた。
会社を守ることに必死で、自分が本当に大切にすべきものを見失っていたのだと。
そして、この気づきこそが、のちの経営の原点へとつながっていくことになる。
「できていない自分」に気づいた日──
久保社長が誓った“弱さを越える”経営
フィロソフィとの出会いは、久保社長にとって「経営者としての転機」であり、「人としての転生」でもあった。
息子の言葉に心を動かされたあの日をきっかけに、久保社長は会社経営と真剣に向き合うようになった。フィロソフィをつくる過程で、これまで自分が従業員に求めてきた指導やルールが、本当に正しかったのかを一つひとつ見直していった。
「挨拶をしっかりしよう」「相手の目を見て話そう」――その言葉自体は間違っていない。
だが、果たして自分自身はそれを実践できていたのか?
久保社長は初めて、自分の心を冷静に見つめ直した。
そして気づいたのは、「フィロソフィとは鏡のような存在だ」ということ。
自分ができていないことを社員に求めても、誰もついてはこない。
“教える”前に、まず“自らが体現すること”。
その原点を、改めて胸に刻んだのだ。
息子の純粋な言葉と、この気づきが重なったとき、久保社長は「弱い自分を乗り越える」という新たな誓いを立てた。
フィロソフィを導入してから約6年。
久保社長は振り返る。
「もしあのとき出会いと誓いがなければ、今の自分も、この会社も存在していなかったでしょう」
学びを深め、誓いを行動に変えることで、自分の弱さとも正面から向き合うことができた。その経験こそが、今の経営の原動力になっている。
久保社長の根底にあるのは、「全従業員の物心両面の幸福」を実現するという信念だ。
人はそれぞれ欲求も価値観も異なる。しかし、人生を懸けてでも全員の幸福を追求する価値がある――久保社長はそう確信している。
そのために、社員には「自分も経営の一員だ」と感じてほしいという。
決められたことに従うだけでは不満が残る。
しかし「ここには自分の責任がある」と思える人は、困難を前にしても前向きに考え、主体的に動ける。
だからこそ、久保社長は日々社員と意見を交わし、経営を共に考える時間を大切にしている。
「全員に主体性を求めるなら、まず経営者自身がその姿勢を示さなければならない」と久保社長は語る。
自分のためだけに行動する人は長続きしない。
人の幸せを自分の幸せと感じられるかどうか。
「誰かに喜んでもらえることが嬉しい」――その純粋な思いこそ、久保社長の最大の才能であり、会社の成長を支える原動力なのだ。

最後に、久保社長に株式会社サキカワの強みを尋ねた。
「当社は“人と人との対面”にこそ、最大の価値があると考えています。AIが進化し、仕事の多くが効率化されても、人の気持ちを感じ取り、寄り添う力は人間にしかできません。だからこそ、私たちは“人としての温かさ”を軸に、会社を発展させていきたいと思っています。」
その言葉には、久保社長の経営哲学が凝縮されている。
フィロソフィを導入してからの6年間、サキカワの経営は大きく変わった。
“数字の成長”だけでなく、“心の成長”を重視する風土が社内に根づき、社員一人ひとりが自ら考え、行動する企業文化へと進化したのだ。
フィロソフィは、単なる理念ではなく、経営の判断軸であり、会社の方向性を導く羅針盤となった。
久保社長自身も「フィロソフィがなければ、今のサキカワは存在しなかった」と断言する。
経営の節目で迷ったとき、心が揺れたとき、常に立ち返る場所がある――それが、サキカワの強さの源だ。
創業から75年。サキカワは今も全社員で学び続けている。
2026年には、さらなる成長を見据えた新たなフィロソフィの策定を計画中だ。
「社員が心から“ここに来るのが楽しい”と思える会社をつくる」
その想いを胸に、久保社長は次の時代へと歩みを進めている。
フィロソフィが生んだ絆と気づきが、これからの経営をより深く、より豊かにしていく。
“人の心を中心に据えた経営”――その道のりはまだ続く。
株式会社サキカワ 〒543-0012 大阪市天王寺区空堀町13番12号
HPはこちら